
■八木秋子 回想談 大平洋戦争下のアナキスト マルキスト永嶋暢子との思い出
この『付・回想談 太平洋戦争下のアナキスト-八木秋子の場合「マルキスト永島暢子との思い出」』は、八木秋子が語ったものを関陽子さん(当時『婦人公論』記者)が書き起こしたものである。
原文は『埋もれた女性アナキスト 高群逸枝と「婦人戦線」の人々 犬塚せつ子・城夏子・大道寺房・松本正枝・望月百合子・八木秋子』1976年9月30日発行 に掲載され、後に八木秋子著作集Ⅰ『近代の<負>を背負う女』に所収された。
原本は、アナキストの雑誌『婦人戦線』(1930~1931)の同人たちが、その雑誌の中心にいて活動した高群逸枝の思い出を40数年たって書いたものが主なもので、同人たちの座談会が加わっている。
(*アナキスト詩人秋山清による「己の足跡を消しつつ生きる 昭和のアナキスト・八木秋子」も収録)
そこに、八木秋子の「永嶋暢子との思い出」が掲載されたのは、この冊子を作る過程で取材した回想をなんとか活字で残したいという関陽子さんの強い思いがあったといえる。それは、八木秋子の永嶋暢子への痛切な思いでもあった。
後に、コスモス忌(秋山清をしのぶ会)において関さんにお訊ねしたところ、「永嶋と同僚だった方は京都の寺尾さん」とうかがった。その寺尾さんとは、後に『京都新聞』で連載された「彼女は満州で死んだ」を読んで名乗りあげてこられた方だった。このような奇跡的なつながりが残されるのも、永嶋や八木が人を惹きつける磁力を持っていることの現れだろう。
なお、原文の明らかな間違いと、表記の一部をよみやすいように言葉を修正し補った。
(注:2013発行の「永島暢子の周縁」に再収録。ただし、この説明文は紙面の都合か掲載されなかった:相京範昭)
■永島暢子と八木秋子の満州時代
1986「パシナⅣ」
原題「案外変わらないね」「幾星霜というところかね」永嶋暢子 八木秋子 編 相京範昭
■永島暢子について 1985「パシナⅡ」 岩織政美
■「重心を共有する女-永島暢子と八木秋子」 1987/5『永島暢子の生涯』に掲載
■『永島暢子の生涯-婦人解放運動の先駆者 郷土の出身者として』の出版案内 1987「パシナⅤ」
■酔談放談-岩織政美さんを囲んで 1987「「パシナⅤ」
■『批判を持つ愛の深さ』永島暢子著作集出版記念会あいさつ 1994/8/3
■「彼女は満州で死んだ」 1994「京都新聞」 中村勝
■永嶋暢子と船木幾政の恋愛 2013「永島暢子の周縁」

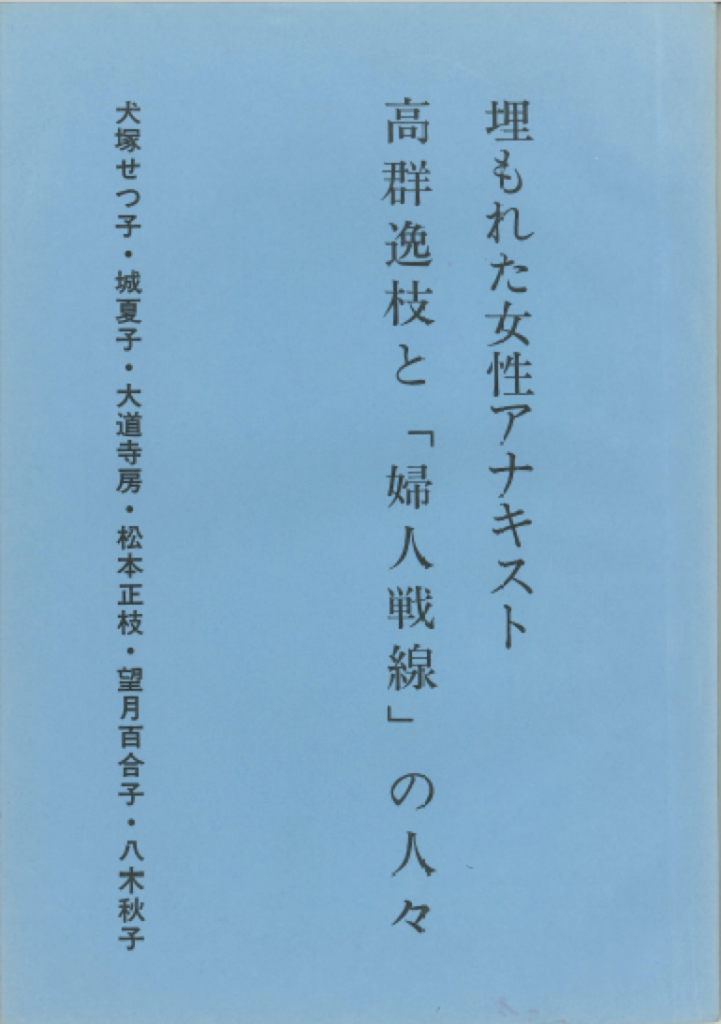
表紙・記念撮影写真・目次・奥付.pdf
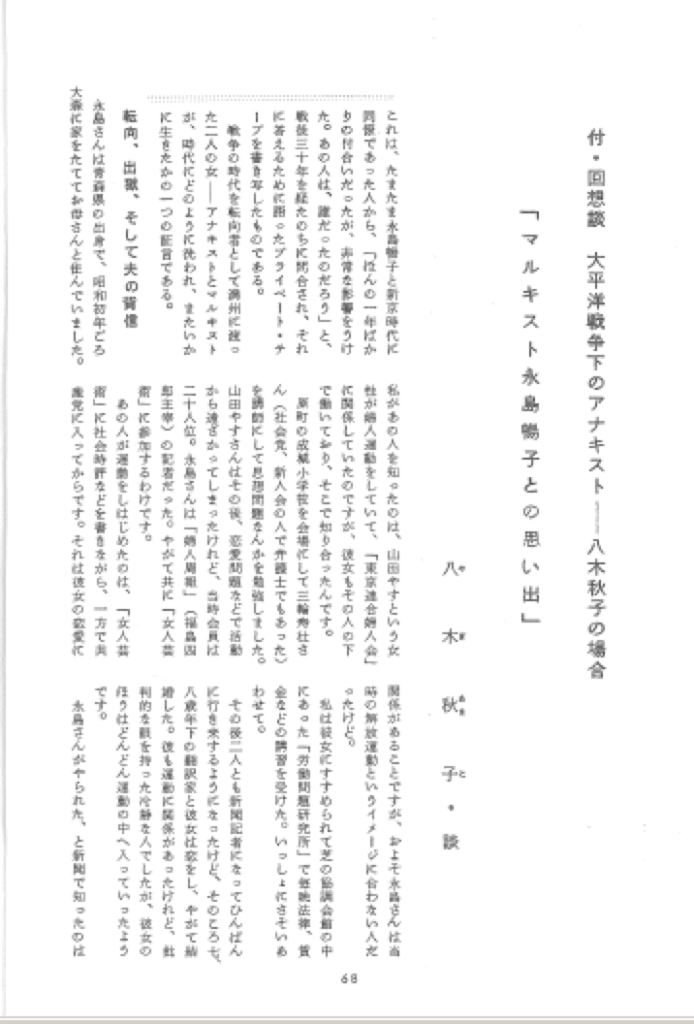
付・回想談 大平洋戦争下のアナキスト-八木秋子の場合
マルキスト永嶋暢子との思い出
八木秋子・談
これは、たまたま永嶋暢子と新京時代に同僚であった人から、「ほんの一年ばかりの付合いだったが、非常な影響をうけた。あの人は、誰だったのだろう」と、戦後三十年を経たのちに問い合わされ、それに答えるために語ったプライベート・テープを書き写したものである。
戦争の時代を転向者として満州に渡った二人の女―アナキストとマルキストが、時代にどのように洗われ、またいかに生きたかの一つの証言である。(関陽子)
転向、出獄、そして夫の背信
永嶋さんは青森県の出身で、昭和初年ごろ大森に家を建ててお母さんと住んでいました。私があの人を知ったのは、山田やすという女性が婦人運動をしていて、「東京連合婦人会」に関係していたのですが、彼女もその人の下で働いており、そこで知り合ったんです。
原町の成城小学校を会場にして三輪寿壮さん(社会党、新人会の人で弁護士でもあった)を講師にして思想問題なんかを勉強しました。山田やすさんはその後、恋愛問題などで活動から遠ざかってしまったけれど、当時会員は二十人位。永嶋さんは「婦人周報」(福島四郎主宰)の記者だった。やがて共に「女人芸術」に参加するわけです。
あの人が運動をし始めたのは、「女人芸術」に社会時評などを書きながら、一方で共産党に入ってからです。それは彼女の恋愛に関係があることですが、およそ永嶋さんは当時の解放運動というイメージに合わない人だったけど。
私は彼女にすすめられて芝の協調会館の中にあった「労働問題研究所」で、毎晩、法律・賃金などの講習を受けた。いっしょに誘いあわせて。
その後二人とも新聞記者になって頻繁に行き来するようになったけど、そのころ七、八歳年下の翻訳家と彼女は恋をし、やがて結婚した。彼も運動に関係があったけれど、批判的な眼を持った冷静な人でしたが、彼女のほうはどんどん運動の中へ入っていったようです。
永嶋さんがやられた、と新聞で知ったのは昭和九年、私が二度目に捕まる少し前で、繊維労働か出版労働だったと思います。一緒に働いていた女工さんたちが、「通称 おばさんがやられた」といって惜んだ、と新聞に出てました。彼女が逮捕されたことを聞いて、労働婦人協会時代に一緒だった三人の友人が集まって彼女の救援のために何かしようと相談したのですが、その時、のちに彼女のライバルになる女性が、懸命に救援をした。救援の連絡のために永嶋さんのダンナさんの所へ通っているうちに、ダンナさんと恋愛関係になったわけです。この女性は「女人芸術」でも永嶋さんや私と友人だった人で、永嶋さんと一緒に検挙されたことのある、アナキスティックな人でした。
彼女は何も知らずに二年と何ヶ月か暗いところに入っていて、転向証明書を書いて出て来たら、ご主人に実は、と告白された。でも永嶋さんは、それを聞いた時、へえ、ありうる、とは考えもしなかった。それから、だいぶ話し合った末、もう彼をとり戻すことが出来ないと知った時、絶望した。健康を害してすっかり弱くなって「女人芸術」同人の辻山ドクターの家に引き取られていた。
その時、「女人芸術」の後の「輝ク」に私の消息が載って、私が獄から出て満州に渡って満鉄に勤めていることを知った。すぐ私の所へ手紙を寄越して、私も満州へ行きたい、ぜひ頼む、って。どういう職場があるか、どういう生き方があるのかと。私が満州へ渡って半年くらい経った時のことでした。
私はダンナと一緒だと思って、とにかくいらっしゃいと言った。何か大きなショックがあったな、くらいに思って。
満鉄の新京支社に勤めていた私の社員住宅に、一人で永嶋さんが渡って来て、その晩、その話を聞かされて驚いたんです。とにかく彼女を励まさなければならない。
当時満州には、日本で転向者として保護観察を受けていたような人たちが大勢いたんです。政府関係にも、特殊会社にも。満州帝国協和会。これは五族協和を標榜する、満州帝国の外郭団体ですが、そこにもいいかげん入っていました。司法部の次長が日本人で、共産党事件の裁判の時に検事だった平田勲で、内地から来たわれわれ転向者の面倒を見ながら保護観察しようというわけだった。満州へ行ったらそういう面倒な関係は全くないんだろうと思っていたのに、動向は逐一わかるようになっていた。ああ、メンドウだって。
そのうち永嶋さんと私はこの平田勲の所へ行くようになって、まもなく関東軍の出していた「月刊満州」という、満州における日本人の生活を知らせる本の記者として彼女は働きはじめた。その後、給料が倍だという理由で満州鉱工技術員協会に移り、そこでかたい記事を書いていましたが、やがて協和会に入りたいといって入ったんです。満鉄の社宅に二人で半年くらい一緒に生活し、やがて別れ別れに家を借りて住むようになった。
昭和十五年ころだったか、新京で満人の子が一人ペストになり、あたり一帯を焼き払って彼女も焼け出され、再び一緒に住んだんです。
その時、突然、彼女が検挙された。ある朝、永嶋さんが協和会へ出かけたその留守に家宅捜索があって、本の二、三冊だけ持っていって、そのあと彼女が引っ張られて、新京の警察に一ケ月半くらい引っ張られた。何の証拠もなく、容疑も何だかわからないうちに出て来たけれど。そういうことがあってから彼女は、もう新京はいやだ、もう少し北の方へ行きたいと言いだした。
そして自分でツテを頼って、北満の東安の協和会へ行った。こんど日本へ帰る時はアムール河を通ってウラジオストックを通って帰るから、って言って引っ越して行ったんです。むこうへ着いたら、紹介してくれた人が憲兵に連れて行かれたと言われた。それですっかり疎外感に悩まされて手紙が来た。そんなやこんなで心配して、あれこれ働いて一年位たって再び新京へ戻ってくるようにしたわけ。がっかりして戻って来ました。首都本部勤務になった。
永嶋さんも、私の内地の時代からの同志の人との恋愛問題もあったりしたのですが、転向者のわたしたちはお互いさまで、そういう過去や現在のことには互いに触れないことにしようということで。
むすばれる恋だと思わない、八木さん、どうして永嶋さんのために忠告しないか、ってまわりの人がいうんです。永嶋さんが非常に純情に歳の若い人を愛しているから、いまのうちに何とか言ったほうがいいって。終りは全うできなくったって、それはその時でいいじゃないか。わたしは口ばしを入れたくないし、私が知っているということで、あの人を窮屈がらせたくないから、っていって何も言わなかった。そうしたら一方の人が転勤になって山奥へ移っていき、自然に終ってしまいました。昭和十八年ごろの話。
昭和二十年八月の満州
永嶋さんは戦後延京(*ママ「新京」の間違いだろうと思われる<相京>)の幼稚園で、ハッシンチフスが流行し、親と死別してた子どもたちを収容して、懸命に世話をしていたんです。そうしたらそこへ、ソ連の兵隊が入ってきて、皆が犯された。みすみす夫の見ている前で奥さんを犯す、というような状態であったと、その場に居合わせた人が、のちに話してくれました。みんな、これは不可抗力のことだから、日本に帰っても、何も言うまい、って申し合せて帰ったのよ、って言っていました。永嶋さんも、あんなことで自殺することはないのに、っていうんですよ。
永嶋さんはソ連っていうものに対して非常な魅力を持っていた。革命っていうこともあったし。だんだん戦局が激しくなって、いよいよ日本が負けるっていう頃になると、八路軍がどこで反乱している、というような情報が協和会にどんどん入ってくる。永嶋さんが、さあ、どうしよう、と私に言い、二人で相談した時に彼女は、わたしは河むこうへいくよ、って言うの。アムール河は満州とシベリアの境。河むこうっていえばシベリアのことでしょ。私はその時、「あんた、甘いねえ。いくら、私たちのような前歴を持った女だって、日本人であることに変わりは
ないんだから、ソ連が歓迎するわけないじゃないか。」って言ったんだけど、ともかく二人とも、中国に残る、って言ったの。
帰ったところで家はないし、両親も死んでいるし。日本に対する執着はなかった。それより、敗戦という事態の中でどういう混乱が起き、どういうことが起るかが想像出来なくて、残って中国がどうなるか、ソ連が入って来てどうなるか、時代の証人になろうじゃないか、って言い合っていたわけです。いざというときは私の社宅の所へ来なさい、どうなるかわからないけど、二人で行動を共にしようって固く約束したんです。
そのうち永嶋さんが、明日の朝から二、三日奉天へ出張することになりそうだって言っていたの。
昭和二十年八月九日、長崎に原爆の落ちた日の朝、関東軍の臨時ニュースがあって、大本営発表、ソ連が、日本に対して宣戦布告したって。その時までは、日ソ関係について甘い考えを持っていたのだけど打ちくだかれた。平和条約を再び結ぶために近衛さんがスターリンに頼みに行くんだってという噂だったけど、ラジオで聞いて、ああ、もうだめだって。もう防げゃしない。それですぐ市民は避難するように、ってことになった。私は永嶋さんと止まろうってことになっていたので、協和会や下宿にTELしたけど通じない、奉天へ行っているらしい。そのうち引き揚げ列車の手配で私の方が忙しくなって来た。
社員は応召にもどんどん出ていくし、北満・東満から社員が雪崩れこんで来た。夕方、家へ帰ったら、課長が来て、駅の列車司令へ行こうという。満鉄の家族の疎開があつて行先ははっきりしないけど、どんどん避難させるという。南新京から一時間、客貨車混合の列車に一台ずつ、行先はどうやら平壌らしい。ソ連がぞくぞく進駐している。男は残り、女と子どもと老人は列車に割り当てる。各自の家の前にふとんのつつみは二つまで、行李は三つ、箱一つまで許す、ってわけ。トラックが来て列車に積み込むって。満鉄は会社じゃない。間一髪って時みんなを運ぶのが使命でしょ。でも、いざという時、自分の社員の家族を優先的に、一時間に一つづつも特別列車を仕立てて、一日十一回も独占して。
わたしは、満鉄にこれだけ精魂傾けて今日まで働いて、ほんとに好きだったけど、これで見限った、って思ったね。憤りを感じましたよ。永嶋さんは奉天へ行っているでしよ。あの人が無事に帰れるかどうかわからないじゃありませんか。方々に行っている人はそれこそ間一髪の所で帰ってこなけりゃならない。だのに足を奪われちゃうわけです。ああ、やっぱり帝国主義の会社だったんだなぁって。いまにして思えばあの当時、大きなスケールで、満鉄の中に米国式の民主主義が育っていた。だから好きだったんですが、満人の社員や朝鮮人社員に冷たかったし。
十日の朝から夜の十一時まで。奉天からもぞっくり来る。あの危機の時に足を独占してしまったじゃないですか。
永嶋さんは奉天にいたのかどうかわかりませんが、同じ町内なので帰って来れば、私の宿舎へ来るはずでしたが、ぜんぜん来ない。私は社宅の家族を次々送り出し、もう社宅街はまっくら。鬼気せまるものがありました。どの家も空家で。そこにわたしだけ一人で、ローソクを立てて待っていました。十一日、十二日。彼女が来たら消費組合に残っている食糧を廻してもらおうと手はずを整えて待っていました。
十三日明方、最後のとり残された応召社員の留守宅と最後まで残っていた少女社員を乗せるから、いっしょに乗って行ってくれ、とたのみに来た。私は残りますから、と言った所、あんたが被護した社員じゃないか、途中まででいいから送って行ってくれ。途中から引っ返していいからって。途中まで、って約束で乗り込みました。(相京注:八木は奉天で途中下車し満鉄の寮に行く、おそらく永嶋を探していたのだろう。その寮で小倉正明と出遭った― インタビュー「俺はパシナの機関士だ / 小倉正明.pdf)
十四日に安東にやっと着いた。ここで引っ返そうとしたけれど、列車がない。十五日、鴨緑江をわたり、二、三時間下った時、班長集まれ、ってわけ。敗戦だって。無条件降伏だって。帰ってみんなに話すとびっくりし、一体これからどうなるか、私たちは満州で子を生み、育てて今日までいて、内地には何もない、って人がほとんどなの。日本へ帰ってもしょうがない、満州へ帰りたい、って人ばっかり。泣き出して。列車中の人の意志は、満州へ引き返したいってことだった。
それでまた列車を逆にしてノロノロと北上して一時間か二時間、鴨緑江の近くまで行った時にストップ。安東から奉天への線で暴動が起きてたいへんな騒ぎで進めないから引き返せって。十日から十一日、十二日に避難した人たちが平壌の沿線に疎開している。そこに合流しようということで、平壌まで戻ったところ、朝鮮では、独立万歳、日本から解放された、ってことで、石を投げこまれたり鉄棒を持っていたりで、平壌に降りられない。しかたなく京城まで行ってしまった。京城もたいへんな殺気。大田まで更に下って、そこにいた日本の部隊に合流。
友だちを裏切ったつらさを抱えて
そこに一ヶ月いた。永嶋さんのことを考えると、どうしていいか、もういてもたってもいられない。再び引き返そうとしたんだけれど、三十八度線をがっちりかためられてもう戻れない。
満州へどうしても帰りたい人たちと一緒に行動しようということで、船を仕立てようということになった。安東まで密航しよう。三十八度線をこえて鴨緑江の近くの輯安につきたい。近所にいた党員の鮮人の細君ってことで、わたしは言葉が出来ないから、おしになりすまして、連れて行って貰うことにした。金がいるってことで、姉の家から盗んでこいっていう指令でした。信じる気にならず、別のルートで満鉄の人と密航の船を探したけど、ついにそれはかないませんでした。
結局、昭和二十年十二月、日本に戻って来てしまいました。
あくる年の末であったか、鉱工技術員協会時代の友人と、神田の美土路町でばったり会い、彼女が自殺した、って聞きました。
一軒残らず被害を受けた、悲惨であったといいます。このことだけは口を割らないって約束をしたっていいます。だから彼女が自殺した時、なんてことだろう、みんなでこうやって何もなかったことにして帰ろうと言っているせつなさったらなかった、死ななくったってよかったのに、って。当時、女の人には、まさかの時のために薬を配ってあった。それを使ったということです。ただ、遺書はなかったけれど、彼女を裏切った夫の写真をふところに入れていた、って。それを聞いた時、彼女の悲しみがどんなに深いものだったか、悟りました。
永嶋さんのところへどうして飛んで行かなかったかと悔まれて。あの鬼気せまる死の街で、夜は出られなかったにせよ。
だからきっと、私が出立したあと、昼間でも永嶋さんが会社へ訪ねて来たり留守宅へ来たにちがいないと思う。その時、わたしが黙って彼女を置いて行ったということで、どんなショックを受けただろうと思うと、それでもう、ほんとに苦しい。
だから、戦後、積極的に職を求めてどのように更正しょうなんて、それどころじゃあない。永嶋さんを裏切ったことに対する自責の念。ああ、友だちに裏切られたという深い憤りと悲しみ、どんなに絶望したろうと思うと、それが申しわけなくて。永嶋さんを一人置いてきたことで、積極的に生きる意欲がなくなった。
なんとかして中国に渡りたいとばかり思って。彼女はほんとにソ連を信じていたのよ。わたしは一九一七年の革命の仕方が間違っているって、よく二人で議論した。それでも彼女は信じていましたからね。
信じていたものすべてに裏切られてしまったという絶望はどんなに大きかったことでしょう。革命の実現していたソ連と、親しい友人であった私と、信じていた同志でもあった夫と。――
この『付・回想談 太平洋戦争下のアナキスト-八木秋子の場合「マルキスト永島暢子との思い出」』は、八木秋子が語ったものを関陽子さん(当時『婦人公論』記者)が書き起こしたものである。
原文は『埋もれた女性アナキスト 高群逸枝と「婦人戦線」の人々 犬塚せつ子・城夏子・大道寺房・松本正枝・望月百合子・八木秋子』1976年9月30日発行 に掲載され、後に八木秋子著作集Ⅰ『近代の<負>を背負う女』に所収された。
原本は、アナキストの雑誌『婦人戦線』(1930~1931)の同人たちが、その雑誌の中心にいて活動した高群逸枝の思い出を40数年たって書いたものが主なもので、同人たちの座談会が加わっている。
(*アナキスト詩人秋山清による「己の足跡を消しつつ生きる 昭和のアナキスト・八木秋子」も収録)
そこに、八木秋子の「永嶋暢子との思い出」が掲載されたのは、この冊子を作る過程で取材した回想をなんとか活字で残したいという関陽子さんの強い思いがあったといえる。それは、八木秋子の永嶋暢子への痛切な思いでもあった。
後に、コスモス忌(秋山清をしのぶ会)において関さんにお訊ねしたところ、「永嶋と同僚だった方は京都の寺尾さん」とうかがった。その寺尾さんとは、後に『京都新聞』で連載された「彼女は満州で死んだ」を読んで名乗りあげてこられた方だった。このような奇跡的なつながりが残されるのも、永嶋や八木が人を惹きつける磁力を持っていることの現れだろう。
なお、原文の明らかな間違いと、表記の一部をよみやすいように言葉を修正し補った。
(注:2013発行の「永島暢子の周縁」に再収録。ただし、この説明文は紙面の都合か掲載されなかった:相京範昭)
